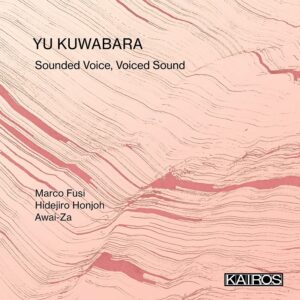BOOKS|日本の建築|藤原聡
 日本の建築
日本の建築
隈研吾 著
岩波新書
2023年11月出版
960円(税別)
Text by 藤原聡(Satoshi Fujiwara)
大きく言えば、隈研吾の建築に対する理念はこの最新刊においても『反オブジェクト 建築を溶かし、砕く』、『負ける建築』などの著作と同様である。すなわち、木造による小さく、弱く、緩く、低く、中と外の分断のない建築の称揚。これは古来の日本建築に備わっていた特質であったが、日本の西欧近代化=合理性とモダニズムが猖獗を極める中でそれらは時代遅れとみなされ、然る後、他の芸術(建築を「芸術」と呼ぶか否かはその作品の実態や文脈によろうがひとまずそう記す)同様、モダニズムへの反動、揺り戻しとしてのポストモダニズム的なムーヴメントが生じ、それらへのある種の再評価の動きが生じる―図式的にはそう説明可能であろう。しかしこれはいかにも事後的/教科書的な記述だ。
もちろん隈研吾がそんな普通に整理された本を書く訳がない。本書で同氏は「従来の日本建築史の退屈は、二項対立にあると感じた」と「おわりに」に記す通り、ひとまず俯瞰的に全体像―そんなものがあるとしての話だが―をざっくり把握するには有効なこの図式から漏れてしまうはるかに細やかなパースペクティヴとして「複数の主体性、地域、階級との闘争と対立によって生成された、多様性をはらんでダイナミックな日本建築史」を提示しようとする。そのためにブルーノ・タウト、ミース・ファン・デル・ローエ、フランク・ロイド・ライト、吉田五十八、村野藤吾らをメインとしつつ多様な人物を補助線として召喚し、そして実際の建築家たる著者の隈研吾がそれらとの関係の中から培われた自身の方法論もが語られるために、その内容は批評家的な明晰さと博識さを披露しつつもそれにとどまらぬ極めて説得力のあるものに仕上がっており、その内容の豊かさは新書とは思えぬほどである。
個人的には、先に日本建築史の退屈を二項対立にあると指摘した隈ならではの重要な記述はアントニン・レーモンドについてのものかと思う。本誌は音楽ファンが主な読者ゆえ一応記しておけば、あの素晴らしく印象的で1度訪れたなら人の記憶に残り続ける群馬音楽センターを設計したのが他ならぬレーモンドだ(高崎芸術劇場に移る前の群馬交響楽団のホームでしたね)。このチェコ生まれの「折衷主義者」(隈)によるMOMAにおける挑発的なバウハウス批判〜レーモンドが日本において関心を抱いた丸太からの千利休、数寄屋造への言及、その丸太の繋がりからの民藝運動、ル・コルビュジエとの対比。また、「レーモンドの丸太に最も影響を受けたのは丹下健三であったように僕は感じる」との指摘には最初に意外、次にはなるほど、と腑に落ちるものがあり、この説得力は「この広漠とした大きな対象(=日本建築/評者注)を分析するための補助線となっているのは、僕という具体的な建築家である」という隈が自らの体験、実感からしたためたゆえだ。ここに僅かながら引用したレーモンドの記述だけでも、本書における射程の広さが分かるのではないか。そして、建築家という存在はここまで深く多様な事象について考えているものなのか、と素朴に驚嘆しもする。
「八年かけて、この一冊の本を書き上げた」「日本の建築という長くて深い歴史を前にして、エッセイのようなものですませたくはなかった」。その隈の想いは十分な形として本書に結実している。これは建築に関心のある方はもちろん、何らかのアートに興味のある方はぜひ読まれたい。示唆と発見に富む。
(2024/1/15)