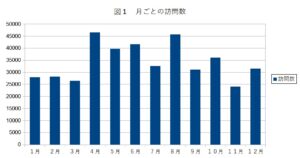私が書く理由|空想する女|能登原由美
空想する女
Text & Photos by 能登原由美(Yumi Notohara)
私には空想癖があるようだ。
幼い頃は、あらゆる「ごっこ遊び」はもちろんのこと、頭の中でいろいろな物語を空想するのが好きだった。その癖が高じていつしかそれを文字で表すようになり、ちょっとした「物語」も書くようになった。そこから小説を書き始め…といきたいところだが、残念なことに、国語が得意というわけではなかった。読書感想文など、賞を取るどころか、先生から褒められた記憶すらない。クラスメイトが感想文で褒められるのを横目で見ながら、いつしか自分には全く文才がないと悟り、「その道」にはすっかり見切りをつけてしまった。書いたものも、いつ、どこへやったのか。全く覚えがない。
 それでも空想することはやめられなかった。ただ、小学生の頃頭に浮かべていた「物語」は、やがて、つかの間の「場面」や「情景」を描くことに変わっていった。例えば、車で山道を通りがかった時のこと。ふと斜面を見上げると、一面の枯木立に陽射しが降り注いでいる。とその瞬間、そこにあるはずのない山小屋が、ふと眼に浮かんできた。陽光が深く射し込んだ小屋の内部には薪ストーブと、蒸気を上げ続けるやかん、そして年老いた男が一人。やかんのカタカタという音と、気まぐれに吹き抜ける風の音以外は何も聞こえてこない。静かな昼下がりだ…。車窓の向こうに流れる初冬の山々を見つめながら、たったそれだけの光景をいつまでも頭の中で繰り返し描いた。10代の私の空想とはそんなものだった。その老人が誰なのか、何をしているのか。「物語」につながるようなものには何故か気が向かわなかった。
それでも空想することはやめられなかった。ただ、小学生の頃頭に浮かべていた「物語」は、やがて、つかの間の「場面」や「情景」を描くことに変わっていった。例えば、車で山道を通りがかった時のこと。ふと斜面を見上げると、一面の枯木立に陽射しが降り注いでいる。とその瞬間、そこにあるはずのない山小屋が、ふと眼に浮かんできた。陽光が深く射し込んだ小屋の内部には薪ストーブと、蒸気を上げ続けるやかん、そして年老いた男が一人。やかんのカタカタという音と、気まぐれに吹き抜ける風の音以外は何も聞こえてこない。静かな昼下がりだ…。車窓の向こうに流れる初冬の山々を見つめながら、たったそれだけの光景をいつまでも頭の中で繰り返し描いた。10代の私の空想とはそんなものだった。その老人が誰なのか、何をしているのか。「物語」につながるようなものには何故か気が向かわなかった。
空想癖は、20代半ばを過ぎても続いていた。「時々一人でよその世界へ行ってしまう」、「宇宙と交信している」とは、友人たちによく言われた言葉だが、それが呆れを通り越して半ば非難の目であることにようやく気づき、自分の悪癖を直さねばと思った。それからは空想するのをやめた。もちろん、物語も書かなかった。
年を重ね、気づけば短歌や俳句を好むようになっていたのは、この空想癖の残滓のせいかもしれない。ただし、自分では詠まない。人が作った歌や句を愛でるだけで十分だ。「その道」の才がないという幼い頃から刷り込まれた意識が、相変わらず自分の生み出す言葉に信頼を置けなくしているのかもしれない。むしろ、誰かが書いた言葉の、その裡に閉じ込められた世界を私の内部で思い切り広げ、ゆっくりと味わう方が良い。
夕紅葉 谷残虹の 消えかかる 小林一茶
遠山に 日の当たりたる 枯野かな 高濱虚子
わずか17文字、あるいはせいぜい31に過ぎない文字から、ありとあらゆる景色が頭の中に映し出されていく。私に山小屋の幻影を浮かばせたあの景色に再び出会うことはないが、こうして文字に書き留められたものは、その「瞬間」を永遠に留めることができる。そればかりか、一茶や虚子が描いた光景に、数十年、数百年後の私が「出会う」ことができる。
雨やんで 庭しづかなり 秋の蝶 永井荷風
17文字という極小の世界に描かれるのは、瞬時の光景ばかりではない。雨上がりの草木の匂い、蝶の舞、その微かな羽音など、荷風が五感を研ぎ澄まして体験した世界を共に味わうことができる。まさに詠み手が生きた時間を、一つの句から再生させることができるのだ。先人たちが残した数えきれない名句から、無限の世界を見ることができる!
私の中に疼いていた空想癖は、こうして他人が書いた歌や句によって満たされていった。
だのに、これまで避けてきた「書く」という行為に今、挑んでいるではないか…。
何度も言うように、私に文才がないことは百も承知だ。だがそれはそれとして、「遺すこと」の重要性は常々感じていた。偉人の生涯や作品の記録にしても、あるいは行政文書や裁判記録にしても、分野は違えど後世のために遺すべきものはいくらでもある。そして、大学時代に音楽の歴史研究を志した私は、研究などで明らかになったことを遺すべく、様々な種類の文書を書いてきた。もちろん、研究を遂行するにも学術論文を書くにも才は必要だけれども、小説家や歌人、俳人のような文才と、求められるものは違う。
そうした中で、ひょんなことから演奏についての評を書くことになった。これも「遺す」ことの一つだと思って引き受けた。
だが、それが単なる記録とは全く異なる次元のものであることに少しずつ気づき始める。当初安易に考えていたようなもの―誰がどこで何を、どのように演奏したのかといった事柄の列挙で終わるようなものではない。あるいは、奏法や解釈をいくら云々したところで、それがどうだというのだろう。そこで鳴り響いていたもの、私自身が体験したものの本質を何一つ言い当てていない。書いたものを読むたびにこうした思いが募り始め、やがて、何を書いてもつまらないと思うようになった。
どうやら、私は思い違いをしていたらしい。単に「遺す」ことだけが目的であれば、楽譜がある。レコードやCD、デジタル・データがある。作品に込められた意図であれば作曲者自身の言葉、演奏について言えば奏者自らが語る言葉で十分だ。けれども、その音楽が鳴り響く瞬間の、その場所に居合わせた者の「体験」はどうやって遺せるのか。その時に見たもの、聞いたもの、感じたもの、その現象についても書き留めなければならないのではないか。そして、感動が大きければ大きいほど、その「体験」を書き遺さなければならないと思う。それはまさに、歌や句と同じではないだろうか…。
 そのことに気づいた時にはすでに、私の乗った舟は港を出てはるか沖を進んでいた。水先案内人も持たずに漕ぎ出した舟が、どこまで進んでも陸地の見えない大海原の上にあることに気づいたのもこの頃だ。竿を差し続けることも苦しいが、方向が見えないことも苦しい。ましてや、自分の乗っている舟がどのようなものであるのかさえ知らない。なんと愚かなことだろう!だが、漕ぐ手を止めるわけにはいかない。今さら舟を降りることはできないのだ。
そのことに気づいた時にはすでに、私の乗った舟は港を出てはるか沖を進んでいた。水先案内人も持たずに漕ぎ出した舟が、どこまで進んでも陸地の見えない大海原の上にあることに気づいたのもこの頃だ。竿を差し続けることも苦しいが、方向が見えないことも苦しい。ましてや、自分の乗っている舟がどのようなものであるのかさえ知らない。なんと愚かなことだろう!だが、漕ぐ手を止めるわけにはいかない。今さら舟を降りることはできないのだ。
今、書いている理由を問われれば、さしあたりこういうことになるだろうか。
ただ、頭上には小さな星が見えている。どこまで行っても頭の上から離れることは決してない。
もしかするとこの航海は、向かうべき方向というものを持たないものなのかもしれない。ただひたすら、そしておそらく永遠に、海を漂い続けるしかないのだろう。けれども、何百光年と離れた宇宙のどこかで、確かに星は光を放ち続けている。私のもとに届く頃にはもはや存在しないのかもしれないが。その時空を超えた果ての世界を頭に浮かべること、それだけが、今の私が舟を漕ぎ続けている理由なのかもしれない。
(2020/10/15)