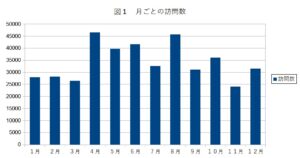忘れがたいコンサート|ジョルジュ・プレートル指揮ウィーン・フィル|平岡拓也
ジョルジュ・プレートル指揮ウィーン・フィル
text & photos by 平岡拓也(Takuya Hiraoka)
忘れ難い音楽、と一言で言っても、さまざまな形がある。整然と構築された論理性の表出に打たれるもの、感情の昂りが我々を別世界に引き上げるもの─そんな中で2010年の秋に聴いたジョルジュ・プレートル指揮ウィーン・フィルによる音楽は、如何とも形容し難い、「これぞ音楽」としか言いようのない体験であり、音楽に対する筆者の接し方をも変化させた。
2010年のウィーン・フィル来日公演は、度重なる指揮者・演目の変更に見舞われた。当初は小澤征爾が全演目を指揮することになっていたが、体調不良で降板。代役としてエサ=ペッカ・サロネンと若きアンドリス・ネルソンスが指揮することが発表されたが、サロネンも事情によりキャンセルとなった。最終的にはネルソンス、フランツ・ヴェルザー=メスト、ジョルジュ・プレートルという3世代の指揮者陣を帯同しての来日となったのである。
この最終決定に、ファンは様々に反応した。サロネン・ファンは嘆き、プレートル・ファンは歓呼の声を上げた。筆者は後者であった。2008年・10年のニューイヤーコンサート登場で脚光を集める以前より筆者はプレートルの大胆不敵な音楽に惹かれていたが、高齢(2010年当時86歳)のため実演を聴くことは叶わないであろうとほぼ諦めていたからだ。東京公演は筆者のスケジュールが合わず、兵庫公演のチケットを確保した。
 曲目はシューベルト『交響曲第2番』とベートーヴェン『英雄』。ウィーン古典派の名曲2篇であり、プレートルとウィーン・フィル双方の魅力を充分に味わえるプログラムであった。
曲目はシューベルト『交響曲第2番』とベートーヴェン『英雄』。ウィーン古典派の名曲2篇であり、プレートルとウィーン・フィル双方の魅力を充分に味わえるプログラムであった。
8年前の演奏について仔細に指摘することは、ここでは控えるが─全篇、耳を最大限にひらき、目を見開いて音の奔流に身を任せた2時間だった。シューベルトの緩徐楽章の蕩けるような旋律美、ベートーヴェンの自在なテンポ操作と終楽章コーダの極彩色の音響バランス等々─今でも手に取るように演奏を思い出すことができる。時代考証を経たアプローチでの古典派演奏が主流となった今、指揮者の個性を強烈に刻印するプレートルの演奏は殆ど聴かれなくなったものであろう。彼の志向する音楽をウィーン・フィルが深く理解し、豊饒な音色で返球する、まさに老匠と名門の稀有な共同作業であった。
何よりも筆者を魅了したのは、プレートルとウィーン・フィルが音が生まれる一瞬一瞬を慈しみ、「音楽をする(musizieren)」喜びをホールいっぱいに振りまいていたことだった。プレートルの指揮は拍節を細かく提示するものではなく、全身を捩って音楽のイメージを伝播させる。ある時はタクトを持たず柔らかく両手で音を抱えるようにして振り、またある時は指先の微細な動きで音のテクスチュアを伝える。とにかく語彙が豊かだ。アンコールのブラームス『ハンガリー舞曲第1番』、J. シュトラウス2世『トリッチ・トラッチ・ポルカ』では両者の自在な関係は極限に達し、プレートルが身悶えすればそのままに旋律のうねりが表出された。この極上の音絵巻に抱かれながら、実演に接することができた僥倖を噛み締めるとともに、「ああ、このような体験はおそらくもうできない・・・」という一抹の寂しさまでもが込み上げてきたことを鮮明に覚えている。
冒頭で記したように、音楽には様々な表現様式があり、受け止め方も多岐に渡る。だが筆者はこの日以来、音楽をする喜びに溢れた演奏を尊びたいと強く思うようになった。理論・様式も当然重要であるが、何よりステージから客席へ「音楽の喜び」が伝わってくることが第一であろう、と。以降バロック、同時代音楽などジャンルの差異を問わず、このことを第一義に置いて聴取を続けている。また、全神経を集中させ「一音も聴き漏らすまい」と臨んだこのコンサートでの鑑賞姿勢を時折振り返り、「聴取において驕りがないか」と時折自省する機会にもなっている。このような変容を筆者にもたらしてくれたプレートルとウィーン・フィルの至芸に、8年越しの感謝の意を伝えたい。
(2018/10/15)