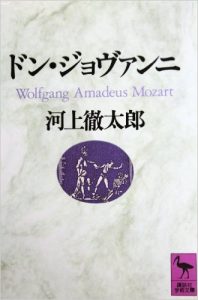カデンツァ|河上徹太郎のこととか。|丘山万里子
text by 丘山万里子(Mariko Okayama)
1年前、本誌創刊号で、批評について書いた。
ここで、再び。
吉田秀和や遠山一行にとって小林秀雄『モオツアルト』は明らかに日本の音楽批評についての一つの啓示であり、とりわけ吉田は最後までそこから水を汲んだ。文体も手法も、だ。遠山も小林に影響は受けたが、はるかに河上徹太郎に心を寄せた。遠山の『音楽有愁』は、河上の『有愁日記』へのオマージュである。
今日の批評の若い世代に、もはや小林も河上も手にとる人は少ないかもしれない。いずれにしろ、河上は、初期に音楽批評や論を多数書いたにもかかわらず、ほとんど言及されることはない。
私にしてからが、この5年ほど遠山の仕事を調べだしてから、河上の存在の大きさを知ったくらい。
河上は小林の『モオツアルト』の4年後に『ドン・ジョヴァンニ』を書いている。
小林がモーツァルトの歌劇を、我が国では上演機会がないが、別段不服はない、「上演されても目をつぶって聞くだろうから。僕は、それで間違いないと思っている。」と鼻であしらい、モーツァルトをシンフォニー作家であり器楽作家だ、と断じているのに、河上はムラムラきた。で、「歌劇作家モーツァルト」を実証しようとしたのが『ドン・ジョヴァンニ』である。
「モーツァルトを交響曲作家か歌劇作家か何れかに決めてしまおうとする企ては、無駄であり、危険であろう。」とまず、異議申し立て、「小林の周到な論法は、十分モーツァルトを論じ尽くしていて、それ自体いうことはない。しかし私には、その上に『ドン・ジョヴァンニ』を聴いた時の眩暈の生々しさがある。それはドン・ジョヴァンニの生命そのものから迸る肉感的なもので、しかもその有機性は、確かに西欧近世器楽曲の無機性の上に立ちながら、それを超えて独自な有機性を持っている。」
にしても、この「眩暈の生々しさ」という出立点は、小林の有名な一節「僕の乱脈な放浪時代の或る冬の夜、大阪の道頓堀をうろついていた時、突然、このト短調シンフォニィの有名なテエマが頭の中で鳴ったのである。」(反・小林派はこれを嫌悪するが)というのと全く同じと言っていい。
小林も河上も、モーツァルトの音が我が身を食むその実感をひっしと握りしめ、敗戦直後、もしくは間もなくの日本の乏しい音源と資料、あらん限りの文献、スコアだけで、それぞれのモーツァルトを描いた。その熱情こそが、批評を自立した文学の域にまで押し上げた力だろう。
そして「脳味噌に手術を受けた様」な小林の震えと、河上の「生々しい眩暈」は、その発火点であり、同時に、今日も疎まれる<印象批評>の原点でもある。
だが、こういう一撃なしに、どんな批評が可能だろうか。
それを印象と呼ぼうと呼ぶまいと、そんなことはどうでもいい。
河上は、『ドン・ジョヴァンニ』を、キリスト教的愛欲の最高の理念(霊と肉)が音楽でしか能わぬ純粋形で示されている、と言いつつ、なお「この反語的操作を理論の世界で構築して見たいという、批評家としての本能的な情熱があり、遊びがあるのだ。」と、執筆の動機を述べている。背景にはキェルケゴールの哲学があった。
4章からなる論考の最終章は、作品解剖となっている。このオペラを「死の絶対的な背景の上に端的に現れた、生命力の諸相である」という理解のもと、登場人物のそれぞれに詳細な分析がなされるが、とりわけ、レポレロに関しての記述には熱が入る。
例の名簿のアリアについて「あらゆる調の中で一番男性的なニ長調四分の四で、伴奏はその主な和絃のアルペジオを奔放にかき鳴らし、緑の葉陰に洩れる初夏の日ざしのような、光輝に溢れた音が眩くばら撒かれるのであるが、ただ一と所、前述の<スペインでは千三人>というクライマックスになると、歌声に合わせて伴奏を太く単純な四部和声に収め、続いてヴァイオリンのユニゾンで主和絃だけの合いの手が入るが、その道化て虚勢をあげているような効果程、見事に一筆でレポレロの風貌を描いたものはない。」
音大で楽曲分析など学ばなくとも、コンサート・ステージの断片しか見ていなくとも、こういうことを書けるのが、書いてしまうのが、批評家というものだろう。
河上は小林の『モオツアルト』の手法を、モーツァルトの音楽のように、「文章もまたその本来の流動しゆく形においてこれを用いることであった。」と述べる。その背後には「音楽評論家の常套手段は、概念や心理の世界を藉りて、比喩によって音楽を文章に翻訳すること」で、「概念による類比では、理論は分析の方向にばかり進み、流れ行く音楽を一たん堰き止めてこれを吟味することになる。小林が最も心して忌み嫌った態度は、この点であるらしく見える。」という指摘がある。
「小林の文章は、独楽を廻し続けるために絶えずこれを鞭でひっぱたくように、モーツァルトの肖像を画くために必要な、揺るぎのない一線一画を形造る文章を次から次へとこれに当ててゆく。すると肖像は益々重厚な立体感を獲、音楽は絶えず流れ続ける。そういう仕組みになっている。」
確かに。
河上が小林を語って面白い一文をもう一つ。
ある時、小林は河上宅へガリアノの名器を持ってきて見せた。二人の共通の知人がその所有者だったそうで、「見るからにカッチリ纏まった、美しい<静物>であった。ただこの楽器には、古い、使いものにならないような弦が三本しか張ってなかった。彼にいわせれば、ヴァイオリンというものは、弾くものではなくて、見るものなのだそうだ。」
と、「ヴァイオリニスト」というこの短文を終えている。
河上と小林が、名器を前に交わす視線がありありと浮かぶ。
遠山は『河上徹太郎私論』で、小林が、批評家とは河上のことを言うので、それにくらべれば自分は精々詩人だ、といったと書き、「河上さんは生きることを批評にした」とも言っているが、私にはやはりこのあたりの意味や深さはよくわからない。「生きることを批評にする」については、それが批評家の業だろう、と自分なりに思うけれども。
そして、それを、他でもない「遊び」と言ったところに、おそらく河上の批評の真髄、遠山の共感があるのだろうな、とも思う。
突拍子もない話になるが、このごろ、私は演奏会評を書きながら、「俳句」みたいなものができたらいいな、と思ったりする。
一撃に発し、対象を射抜く言葉。広大無辺な宇宙を抱く、美の結晶。
はるか昔、作曲家の松村禎三氏とソビエトの現代音楽祭に同行したことがある(その頃、私は松村禎三論に取りかかっていた)。会場への道すがら、私は畏れ多くも、松村氏と俳句の詠みあいをして遊んだ。
氏は「旱夫」(ベートーヴェンのフィデリオに由来)という号を持つれっきとした俳人である。句集も2冊出している。
私は、別に俳句の素養などないが(母は中村汀女に可愛がられ、その句集の編纂者でもあったので、子供の頃からなんとなく目にしてはいたが)たまに誰かと、小さな子供とでも、歩きながらこういう言葉遊びをする。
とにかく目に付いたもの、浮かんだ言葉をぱっぱとつなぎ合わせ、どんどん松村氏に投げつけた。氏はウンウン困惑し、私は、私のは「吐き捨て句」なんですよ、アハハと笑った。
それと、「俳句」みたいな評、というのは全然違う話だし、河上や遠山の「遊び」と、こういう遊びとは、やっぱり全然違うだろう。でも。
松村氏と遊んだ句の記憶は、書き留めたわけでもなし、何も残っていない。
私の好きな、氏の句を一句。
「空間がくづれる凍鶴歩き出し」
ああ、こういう評を書けたら。
(2016/10/15)